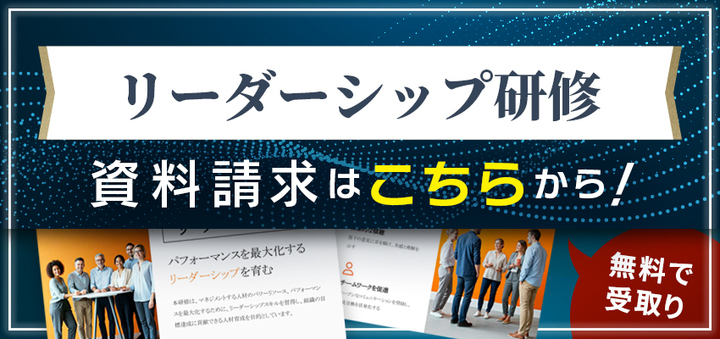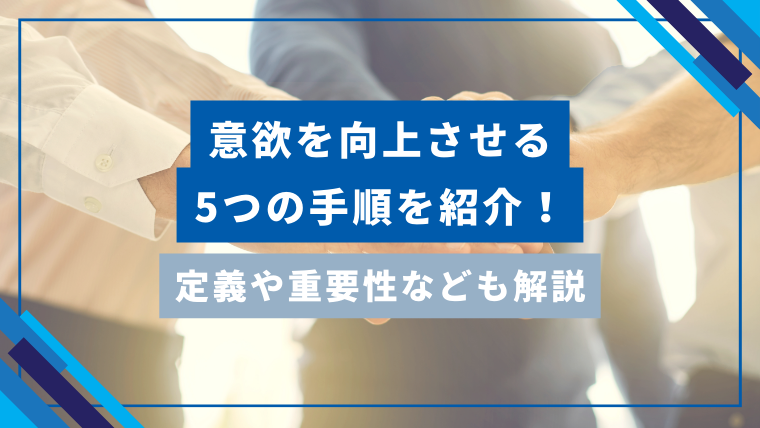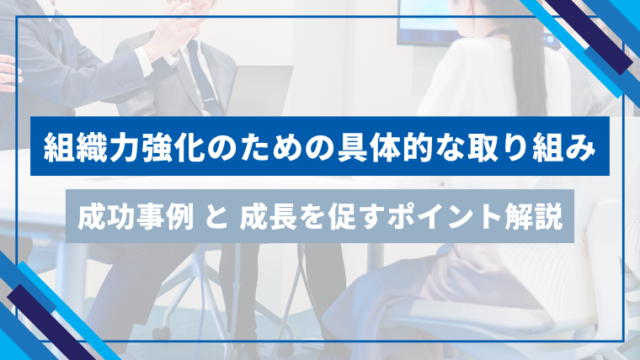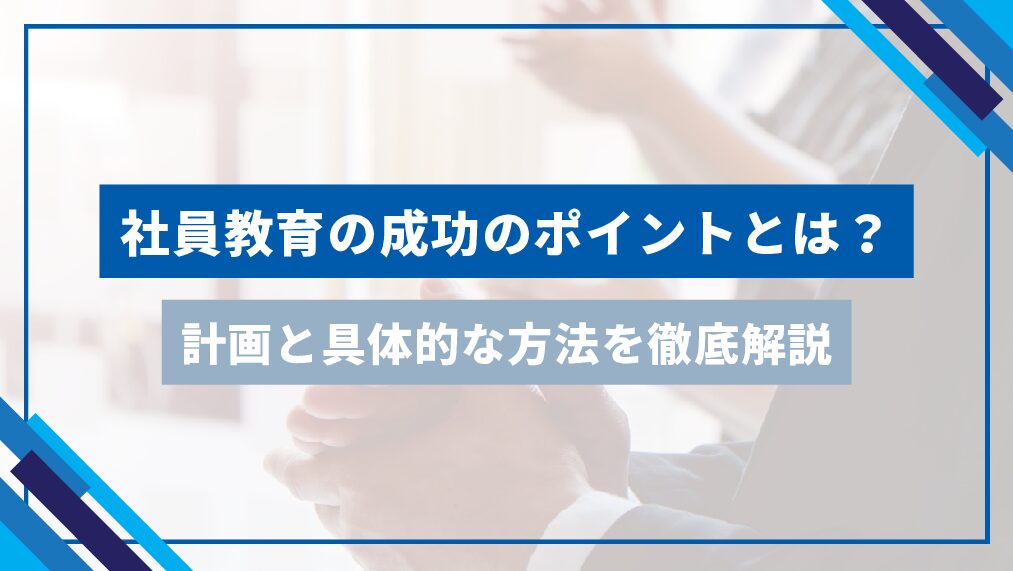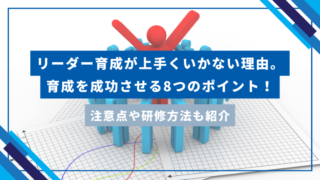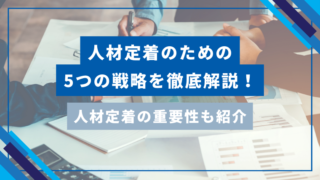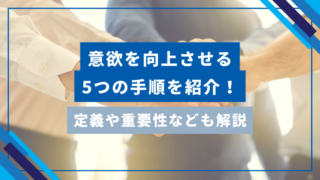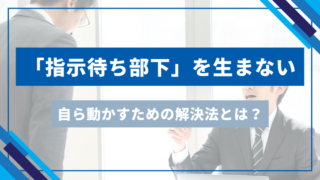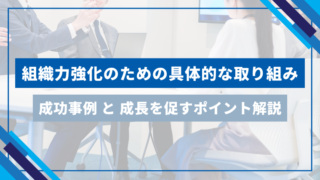会社が成長するためには、社員の意欲を向上させなければいけません。本記事では、意欲が高い社員の特徴をご紹介します。そのうえで、意欲を向上させるための手順を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
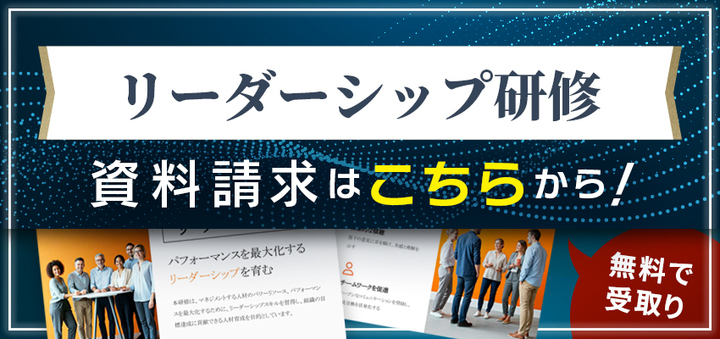
1.社員の意欲が向上する重要性
経営者だけが意欲的に仕事に取り組んでも、会社の成長につながりません。1人1人の社員が「仕事に対する熱意・意欲」を持っていなければ、良い企画が生まれず、売上は伸びないでしょう。
1. 企業にとっての意義
以下は、社員の意欲向上が企業にもたらす主なメリットです。
- 生産性向上
- 離職率低下
- 顧客満足度向上
意欲・モチベーションが高い社員は、そうではない社員よりも、会社への貢献度・生産性が向上します。意欲の高い社員を増やせば、同じ人数でより多くの仕事を遂行できる(同じ量の仕事をより少ない人数で回せる)ようになり、企業の業績が拡大するでしょう。
離職率が低下する(定着率が高まる)ことも、企業にとってのメリットです。少子高齢化により、優秀な人材を確保するのが困難になっている昨今、社員の意欲を高める施策が欠かせません。
また、社員の意欲が高い会社では、社内の雰囲気が良くなりますが、そのことは顧客に伝わります。その結果、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
2.意欲が高い社員の特徴とは
以下、意欲が高い社員の特徴を2つご紹介します。
1. 周囲への影響力
意欲の高い社員は、同僚にポジティブな影響を与えることを認識しておきましょう。多くの社員のモチベーションが高い職場では、日頃から社員同士のコミュニケーションが円滑に実施される傾向があり、良好な人間関係が構築されます。
そして、ソーシャル・サポート(「落ち込んでいる同僚を励ます」「道具を貸し借りする」「業務を効率化するための体制を整える」「課題解決につながる情報を教え合う」など、社会的な関係の中でやりとりされる多種多様な支援)が機能し、職場全体の雰囲気が向上します。
2. 高い生産性
ハーバード・ビジネススクールのテレサ・アマビール氏の研究によると、「内発的モチベーション」を有する人材は、そうではない人材に比べて、より高いパフォーマンスをもたらすことが示唆されています。
意欲が高い社員は、効率的に業務を遂行できるほか、創造的な問題解決能力も有します。職場全体の生産性向上につながるので、多くの社員の意欲を向上させるために、さまざまな施策を実施しましょう。
3. 手順①:意欲低下の原因を知る
以下、社員の意欲を向上させるための手順をご紹介します。まずは、社員の意欲の低下につながる原因を知ることからスタートしましょう。
1. 業務の多様性と負担
人材の確保が困難な昨今、中小企業では、1人が複数の役割を担うこともあるでしょう(例えば、「経理担当者が接客や予約管理も実施する」など)。
このような中小企業の特性(担当する業務の多様性)は、従業員の負担を増加させ、肉体的・精神的疲労が蓄積し、意欲低下につながる場合があります。
2. キャリアパス・評価制度の不明確さ
キャリアパス・評価制度の不明確さは、意欲低下の原因となる重要なリスクです。仕事を評価される際に、平等性や正確性のない評価制度に則って判断されると、社員のモチベーションは向上しません。むしろ日頃の研鑽が認められないことにより、大幅にやる気を失ってしまいます。
不適切な評価制度が実施されていると、社員の意欲が低下し、企業全体の生産性が下がるのでご注意ください。
3. コミュニケーション不足
中小企業では、大企業に比べて、少人数のチームで仕事を遂行することが多いのではないでしょうか。
少人数組織であるがゆえに業務の遂行に追われ、イベント(飲み会、社員旅行)などの開催が困難になり、密なコミュニケーションを図れない場合もあるでしょう。その結果、社員の意欲低下につながることがあります。
4. 手順②:意欲向上のための環境づくり
意欲が低下する原因を把握できたら、社員の意欲向上につながる環境づくりに取り組みましょう。
1. オープンコミュニケーションの促進
フリーアドレス制やオープンスペースを導入すると、部署を超えて、社員同士(上司と部下)のコミュニケーションが促進されます。
コミュニケーションが密になれば、社員は会社の経営方針や上司の指示の内容を理解・納得しやすくなり、労働意欲が高まるでしょう。
2. 表彰制度の導入
社員のモチベーションを高めるために、「月間MVPの選出」「部門別の成果発表会」など、表彰制度を導入することもご検討ください。
外部機関と連携して実施することも可能です。例えば、介護事業を営む企業が、高齢者住宅経営者連絡協議会主催の表彰制度「リビング・オブ・ザ・イヤー」にエントリーし、グランプリを受賞したことで、社員の仕事に対するモチベーションが高まったという事例があります。
5. 手順③:個々の成長を支援
「社内研修の実施」「外部セミナーへの参加支援」「キャリアパスの明確化」といった個々の成長をサポートする施策を導入することは、社員の意欲の向上につながります。
1. 社内研修の実施
「月に1回」「2週間に1回」など、定期的に社員研修・社内勉強会などを開催しましょう。
なお、研修・勉強会で取り上げる内容は、社員のニーズに合わせることが重要です(例えば、接客担当者に対しては、接客マナーに関する研修・勉強会を実施)。
2. 外部セミナーへの参加支援
テーマによっては、社内で対応できないこともあるでしょう。その場合は、外部のセミナー・研修への参加を促し、費用の補助を実施することもご検討ください。
例えば、社内にITに詳しい人材がいない場合は、ITスキル向上に役立つ外部セミナー・研修に参加するための費用を補助し、社員にスキルアップを促してはいかがでしょうか。
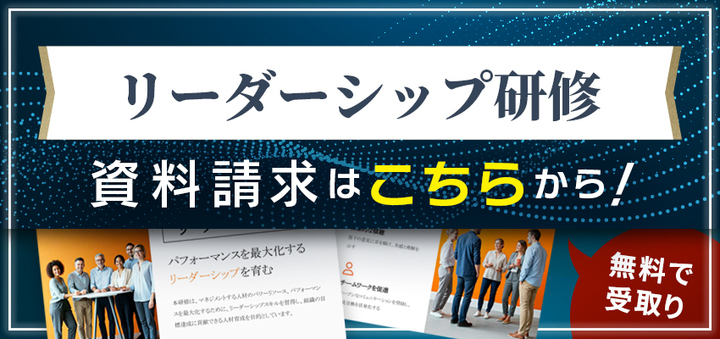
3. キャリアパスの明確化
キャリアパスを明確化することも重要です。5年後のキャリアプランの作成をサポートし、社内でのキャリアアップの具体的な道筋を示してください。
なお、事前に「経験の棚卸」「長期的なキャリア像の自己申告」などを社員に求め、それをベースに面談を実施しましょう。
6. 手順④:リーダーシップを高める
社員の意欲を引き出すためには、上司のリーダーシップを高めることも重要です。
1. 適切なフィードバック
上司は、強権的に部下を統率するのではなく、適切にリーダーシップを発揮するべきです。具体的で建設的なフィードバックを実施し、個々の社員のモチベーション・可能性を引き出してください。
なお、「月に1回」「2週間に1回」など、定期的に実施するほか、突発的な問題が発生した場合は、その都度、フィードバックを実施しましょう。
2. 目標設定とサポート
目標を設定する際は、以下に示す「SMART」の5要素を意識しましょう。
- S(Specific):目標の内容を具体的に定める
- M(Measurable):測定可能な目標を設定する
- A(Achievable):達成できる目標を設定する
- R(Related):経営目標に関連した目標を設定する
- T(Time-bound):いつまでに達成するのか、期限を明確にする
なお、定期的にミーティングを実施し、上司と部下とで話し合い、状況を踏まえて目標を見直すことが大切です。
3. 1on1ミーティングの実施
1on1ミーティングとは、直属の上司などと部下が一対一で実施する面談で、1回15~30分程度、週1回~隔週1回程度の頻度で実施されるケースが多いです。なお、上司の代わりに、メンターが対応する場合もあります。
こまめにコミュニケーションを取り、現状認識のすりあわせをし、情報交換をすることで、信頼関係を築き、社員のモチベーションを高めましょう。
7. 手順⑤:評価制度の見直し
社員の意欲を向上させるためには、評価制度を見直すことも欠かせません。明確な評価基準を設定し、定期的に評価面談を実施しましょう。
1. 明確な評価基準の設定
主観的な基準ではなく、数値化できる客観的な評価基準を設定してください。どのような項目に関して、どのような基準で評価が実施されるのかを、明確かつ具体的に示しましょう。
評価の枠組みをブラックボックス化せず、「何をどうすれば評価されるのか」を知ることが可能な状態を実現すれば、モチベーション向上につながります。
なお、評価のルールを定めても、評価者(上司など)が恣意的・主観的に運用しては意味がありません。事前に評価者に対する研修・説明会を実施し、人事評価の意義や評価者の役割などを伝え、主観を排した客観的評価を実現しましょう。
2. 定期的な評価面談
「四半期ごと」など、定期的に評価面談を実施しましょう。評価面談は、上司と部下がコミュニケーションをとるチャンスであり、信頼関係の醸成および意欲向上につながります。
なお、面談を実施する前に、面談シートを作成してください。漏れがないように、評価者が何を話すのか、部下に何を質問するのかを明確に決めておきましょう。また、面談シートを保存し、評価者が変わっても、これまでの経緯を確認できる体制を構築することが大切です。
3. 効果的な評価制度構築のために
「営業」や「デザイナー」など、多種多様な職種が混在する企業や、古くから同じ評価制度を継続してきた企業の場合、「360度評価」や「MBO」といった最新の手法を取り入れて、平等な制度を構築することが困難なケースもあるでしょう。
なお、360度評価とは、上司に加えて同僚や部下など、あらゆる角度から評価する手法です。また、MBOとは、事前に評価者(上司)と被評価者(部下)の間で目標に関する合意を結び、その目標の達成度合いで評価を実施する手法です。
「自力では、効果的な評価制度を構築できない」と感じる場合は、さまざまな事例を経験している「人事のプロ」に外部委託することも選択肢としてご検討ください。
8. まとめ
経営者だけが意欲的に仕事に取り組んでも、限界があります。会社が成長するためには、1人1人の社員が「仕事に対する熱意・意欲」を持って取り組まなければいけません。
社員の意欲を向上させるために、まずは「意欲低下の原因」を知ることから開始しましょう。そのうえで、意欲向上のための環境を整え、個々の成長を支援し、評価側(上司など)のリーダーシップを高める施策を講じてください。そして、評価制度の見直しも実施しましょう。社内で対応しきれない場合は、外部に依頼することも選択肢として検討するべきです。
なお、意欲を向上させるための施策は、短期目線ではなく、PDCAサイクルを回して施策の内容を改善しながら中長期的に取り組みましょう。