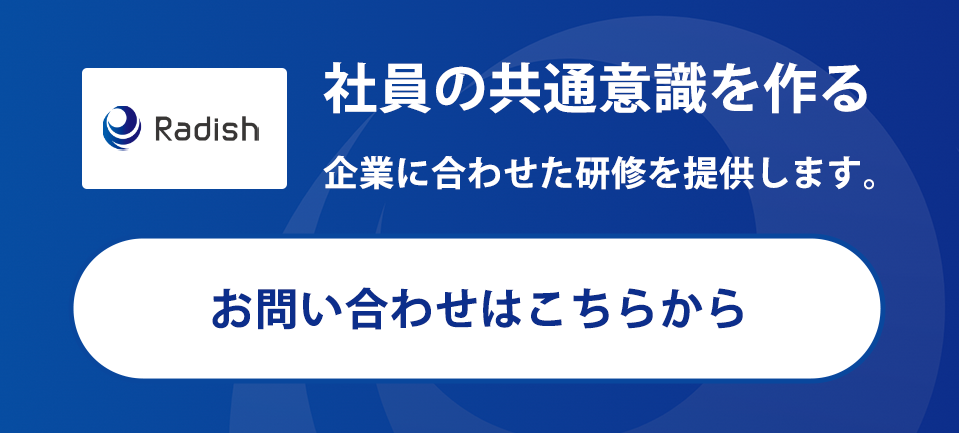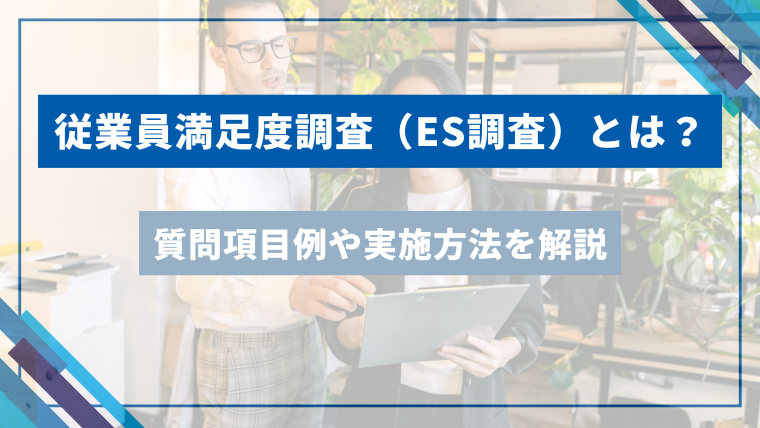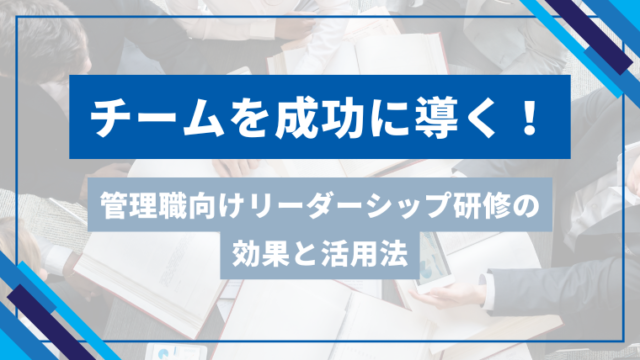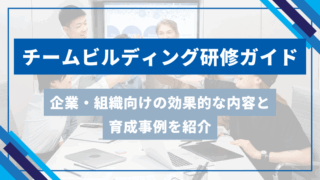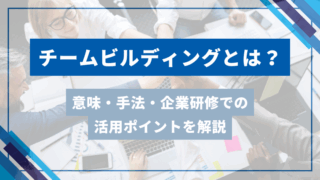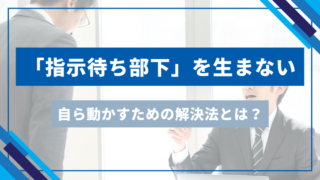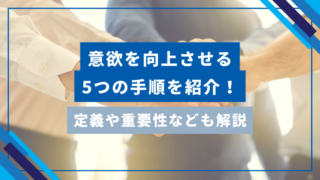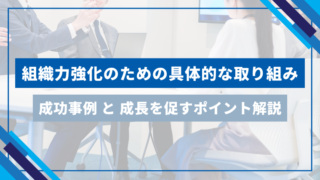従業員満足度調査(ES調査)は、社員が自社に対してどのような意識を持ち、どのような不満や期待を抱いているかを把握するための手法です。近年では、離職率の低下やモチベーション向上、人材定着などの観点から、多くの企業が重要な組織施策のひとつとして導入しています。
本記事では、従業員満足度調査の目的や効果、調査で使用される質問項目の設計例、実施手順、さらに得られたデータの分析方法と改善への活用ポイントまで、実務で役立つ情報を解説します。
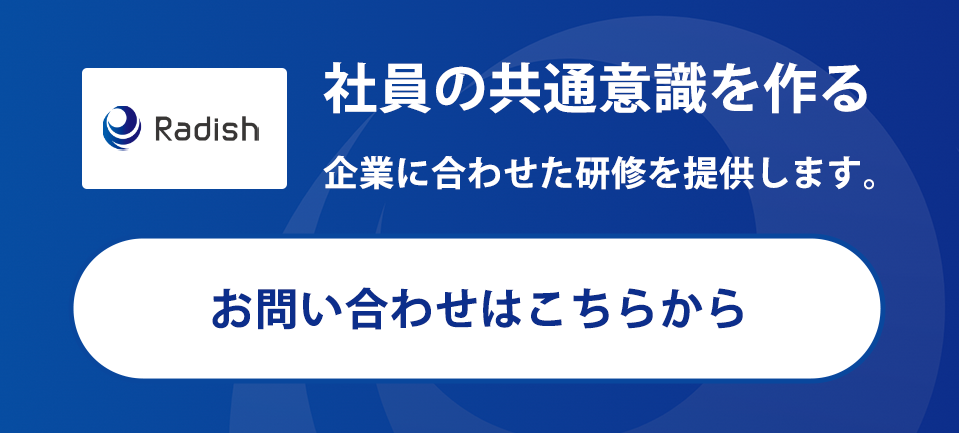
従業員満足度調査(ES調査)とは

従業員満足度調査(Employee Satisfaction Survey/ES調査)は、従業員が自社に対して抱いている満足や不満、期待、信頼感などを明らかにするためのアンケート調査です。給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、仕事内容、職場の人間関係、評価制度、上司への信頼、組織文化など、幅広い観点での満足度を測定します。
企業にとって、従業員の本音を可視化し、組織課題を発見・改善することが最大の目的です。近年では、エンゲージメント調査との違いが議論されることもありますが、ES調査は主に「今の状態への満足度」に焦点をあてる点が特徴です。
実施された調査結果は、定量的なデータとして集計・分析できるため、感覚的な人事判断に依存しない施策設計が可能になります。また、全社員を対象とすることで、組織全体の傾向や部署ごとの比較も行いやすく、データに基づいた人事戦略の基盤としても有効です。
満足度調査の目的と企業にとっての重要性
ES調査は単なるアンケートではなく、経営層や人事部門が従業員の声を事業成長に活かすための情報基盤です。主な目的は以下の通りです。
- 従業員がどの点に不満を感じているかを把握する
- 社内制度や職場環境の改善点を明確にする
- 離職率の上昇や業績低迷といった経営課題の背景を分析する
- 社員のやる気やモチベーションに関わる要因を探る
調査を継続的に実施することで、組織の変化を数値として追跡しやすくなるため、中長期的な人材戦略の立案にも役立ちます。また、社員が自身の意見が反映されていると感じることで、企業への信頼感や帰属意識の向上にもつながります。
従業員満足度が与える組織への影響
従業員満足度が低下した状態を放置すると、さまざまな形で業績に悪影響を与えることがあります。たとえば、業務の生産性が下がったり、チームの協力体制が崩れたり、最終的には優秀な人材の離職にもつながります。
一方で、従業員が職場環境に対してポジティブな意識を持つようになると、仕事への主体性が高まり、部門間の連携も円滑になります。
具体的なプラスの効果としては以下が挙げられます。
- 離職率の低下
- 顧客対応品質の向上
- 組織への信頼や一体感の醸成
- チームマネジメントの安定
- 新入社員の定着率の向上
企業が「人が辞めない組織」から「人が育ち、活躍できる組織」へと変わるためには、従業員満足度の可視化と改善が不可欠です。
従業員満足度調査の主な質問項目と設計ポイント

従業員満足度調査の質を決めるのが、質問項目の設計です。どのような情報を得たいかを明確にし、それに応じた質問を設定することで、調査の有効性が大きく変わります。質問があいまいだったり、偏りがあると、結果の分析が難しくなり、施策にもつながりにくくなります。
調査の設計時には、組織が抱える課題を仮説として立て、その仮説を検証できるような項目を設定することがポイントです。ここでは、よく使われる質問項目と、設計の際に意識すべきポイントを紹介します。
質問項目の例とカテゴリー別の設計例
従業員満足度調査では、項目を大きく分類し、それぞれのカテゴリーで複数の質問を設定します。以下は代表的なカテゴリーと質問例です。
職場環境・設備に関する項目
- 職場の作業環境(デスク、設備など)に満足している
- ITツールやシステムは業務効率化に役立っている
仕事内容・役割に関する項目
- 自分の業務内容にやりがいを感じている
- 自分の役割や目標が明確になっている
上司・マネジメントに関する項目
- 上司は業務の指示が明確で、サポートも的確である
- 上司との信頼関係がある
人間関係・チームに関する項目
- チーム内のコミュニケーションは良好である
- 困ったときに相談できる人がいる
人事制度・評価に関する項目
- 人事評価の基準は納得感がある
- 昇進・昇格の仕組みは公平だと感じる
キャリア・成長に関する項目
- 自身の成長を支援する機会がある
- スキルアップや研修の機会が用意されている
企業文化・経営層に関する項目
- 会社の理念や方針を理解し、共感している
- 経営陣の発信が社内にしっかりと伝わっている
福利厚生・待遇に関する項目
- 給与水準に満足している
- 福利厚生制度は生活を支えてくれている
このように、カテゴリー別に設計することで、分析時にも原因の特定がしやすくなります。
良い質問の条件と設問設計時の注意点
調査の精度を高めるには、質問そのものが的確であることが絶対条件です。以下に、良い質問を作成するためのポイントを挙げます。
- 1つの質問で複数の意味を含まない
(例:給与と評価を一緒に尋ねない) - 曖昧な表現を避け、具体的な文言を使う
(「ある程度」などは避け、明確に) - 5段階や7段階などスケールを統一する
質問ごとにスケールが異なると、回答者が混乱する - 自由記述欄を設け、定量と定性の両方で把握する
- 否定形や誘導的な質問は避ける
(例:~と思いませんか?)
また、回答のしやすさも大切です。スマートフォンで回答する社員が多い場合、設問の文字数やページ構成にも配慮が必要です。設計段階から、誰でも回答しやすいフォーマットを意識することが、回収率を上げるうえで重要なポイントとなります。
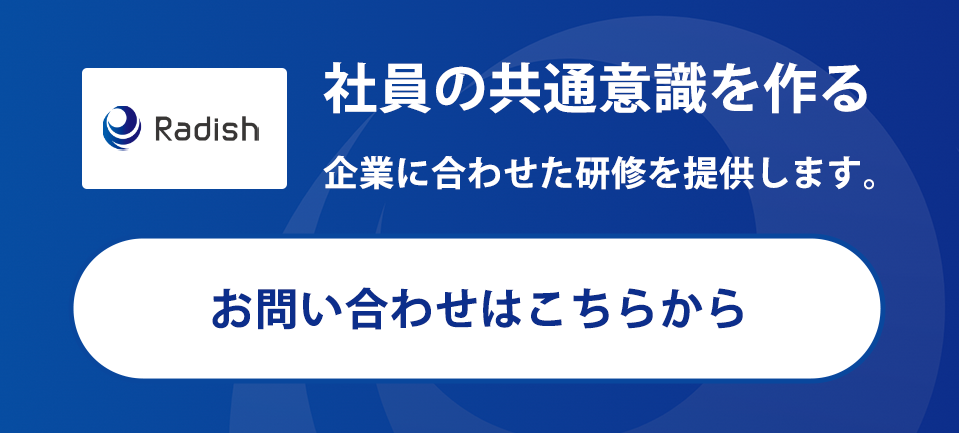
満足度調査の実施方法と運用手順

従業員満足度調査を効果的に行うためには、事前準備から実施、集計、結果の活用に至るまで、一連の流れを明確に設計することが重要です。調査そのものを実施することが目的ではなく、調査結果をもとに具体的な改善アクションにつなげることが最終目標となります。ここでは、調査実施時の基本的な流れと、注意すべきポイントを解説します。
調査準備から集計・分析までの流れ
満足度調査の実施には、以下のようなステップが一般的です。
調査を通じて得たい情報を明確にします。モチベーションの源泉を知りたいのか、人間関係に課題があると見ているのかなど、焦点を定めることがスタートラインです。
目的に基づいて、質問項目を作成します。全社共通の設問に加え、部署や職種ごとにカスタマイズした設問を用意することで、より実態に即した情報が得られます。
アンケート形式は主にオンラインで行われますが、職場環境によっては紙での対応も検討します。回答の匿名性を確保することで、本音の回答を得やすくなります。
調査期間を定め、回答が集まるようリマインドを行います。上司やチームリーダーによる呼びかけも効果的です。
回答結果を集計し、傾向を分析します。部署別や年代別などで分けて比較することで、隠れた課題が浮かび上がります。
分析結果をもとに、具体的な改善施策を設計します。重要なのは、調査結果を活かして実際に変化を起こすことです。
調査は一度きりではなく、継続的な実施とフィードバックの仕組みを整えることで初めて効果を発揮します。
ツール選定と回答しやすい環境づくり
調査の成否は、使用するツールや環境整備にも大きく左右されます。特に、現場で働く社員がストレスなく回答できる状態をつくることが、回収率と回答の質を高める鍵です。
ツールの選定
Webアンケートツールを利用する場合、以下の点を基準に選ぶとよいでしょう。
- スマートフォンやタブレットに対応している
- 結果を自動でグラフ化・分析できる機能がある
- 匿名性の確保がしやすい
- 社内ポータルやメールと連携して配信できる
一部のクラウド型人事サービスでは、満足度調査機能が標準搭載されており、導入から実施・分析までワンストップで行えるものもあります。
回答しやすい環境整備
業務の合間に無理なく回答できるようにするためには、以下の工夫が効果的です。
- 回答時間の目安を明記する(例:5分以内)
- 調査対象に合わせた言葉づかいを工夫する
- スマートフォンでも操作しやすいUIを選ぶ
- 調査実施の意義をしっかり社内で伝える
特に重要なのは、「回答しても何も変わらない」と社員に思わせないことです。調査の目的や、結果をどう活用するのかを明確に発信し、参加する意義を共有することで、より前向きな回答が得られやすくなります。
調査結果の分析と改善への活用方法
従業員満足度調査は、実施して終わりではありません。最も重要なのは、得られたデータをどのように分析し、改善に結びつけていくかという運用の部分です。正しく読み取り、具体的なアクションにつなげなければ、調査の意味が薄れてしまいます。
ここでは、調査結果の分析方法と、そこから得られた情報を活用して、組織を前進させるための考え方を解説します。
よくある課題とその読み解き方
調査結果から浮かび上がる課題には、いくつかの傾向があります。数値の変化や低評価の集まった設問から、組織のボトルネックになっている部分を特定することが大切です。
よく見られる課題例
- 人間関係の希薄化:チーム間・部署間のつながりが弱く、孤立感を感じている
- 上司への不信感:マネジメントに対する納得感が低く、サポートの質にばらつきがある
- 人事評価への不満:評価基準が不明確、努力が報われていないと感じている
- キャリアパスの不透明さ:将来の成長イメージが描けず、離職のリスクが高まっている
- 業務負荷の偏り:一部社員に仕事が集中しており、不公平感が生まれている
これらの傾向を把握するためには、単純な平均点だけでなく、部門別・年代別・職位別のクロス集計を行い、どの層に課題が集中しているのかを深掘りすることが求められます。
また、自由記述欄に記載された社員の声には、数値だけでは見えないリアルな課題や改善のヒントが含まれていることが多いため、丁寧な読み込みと分類が必要です。
効果的な施策とモチベーション向上へのつなげ方
課題が明らかになったら、具体的な改善策を検討します。改善策は大がかりである必要はなく、すぐに始められる小さなアクションでも大きな変化を生むことがあります。
改善につながる施策の例
- 定期的な1on1ミーティングの導入:上司との対話機会を増やし、信頼関係と心理的安全性を醸成する
- 業務の棚卸と再分配:業務量に偏りがある場合は、プロセスの見直しや人員配置の調整を行う
- キャリア支援制度の整備:社内公募制度や社外研修への参加支援など、成長機会を見える化する
- 評価制度の透明化:評価基準の明文化、評価者研修の実施、フィードバック機会の増加
- 社内コミュニケーション施策の強化:部門をまたぐ情報共有の場を設ける、社内報やチャット活用など
中でも特に効果的なのが、従業員同士のコミュニケーションを活性化する取り組みです。調査結果で人間関係や連携に課題が見られた場合は、研修やワークショップなどを活用し、対話の場をつくることが大きな改善効果を生み出します。
重要なのは、調査のフィードバックを迅速に行い、社員に「自分たちの声が経営に届いている」と実感してもらうことです。そのうえで、施策の進捗を定期的に共有することで、信頼関係とエンゲージメントの向上につながります。
従業員満足度調査は、職場の課題を見える化し、改善につなげるための有効な手段です。調査結果をもとに適切な施策を行えば、離職率の低下やモチベーションの向上といった成果が期待できます。大切なのは、従業員の声をきちんと受け止め、行動に移すことです。継続的な調査と改善を通じて、社員が安心して働ける環境を整えることが、企業の成長と安定につながります。