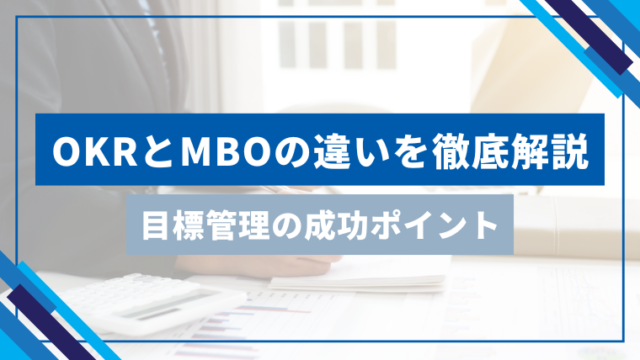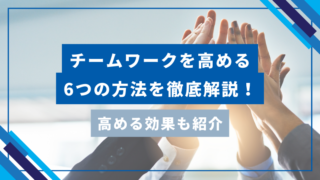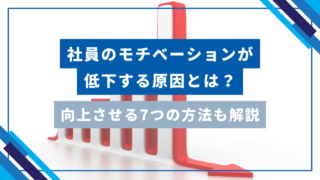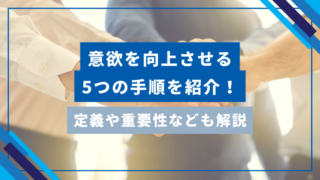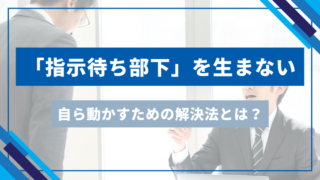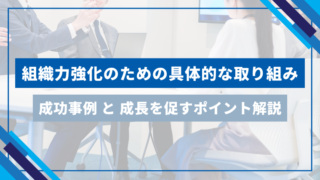本記事では、主に経営者や人事担当者に向けて、以下の内容を解説していきます。ぜひ参考にしてください。
- 360度評価が注目されている理由
- 実施するメリット
- 導入ステップ
- 評価項目例
- 注意するべき点
1. 360度評価とは?
360度評価とは、あらゆる角度から(上司だけではなく、同僚や部下、他部門の関係者などの視点も取り入れて)社員を評価する手法です。
上司以外の視点も含めて多面的に評価することから「多面評価」とも呼ばれており、近年、導入する企業が増加しました。
1.1 従来の評価方法との違い
これまでは、多くの企業で「直属の上司が部下を評価する手法」が用いられてきました。しかし、この方法では、上司の先入観・価値観に影響される可能性があり、公平な評価が実施されるとは限りません。
そこで、従来の評価方法の問題点を克服するために、「1人の上司」の視点だけではなく、さまざまな関係者の視点を取り入れた360度評価が活用されるようになりました。
2. なぜ今、360度評価が注目されているのか?
360度評価が注目されている理由・背景事情を3つご紹介します。
2.1 働き方の多様化
新型コロナウイルス感染症の流行や、厚生労働省が「働き方改革」を推進してきたこともあり、多くの企業でリモートワークやフレックスタイム制が実施されるようになりました。
働き方が多様化すれば、さまざまな立場・価値観の社員(「育児・介護との両立を重視する社員」「プライベートの時間を確保したい社員」など)が業務に関わることになります。
多様なバックグラウンドを有する社員を正しく評価し、能力を発揮してもらうためには、旧来の「直属の上司の視点」だけでは不充分です。同僚や他部署の社員などの視点も取り入れた360度評価を実施しなければいけません。
2.2 組織の平坦化
近年、さまざまな企業で、迅速な意思決定を実現するために、「組織のフラット化」が進行しています。
「部長」「課長」「係長」といったピラミッド型の組織内階層構造の減少に伴い、従来の「直属の上司が部下を評価する方法」では充分に評価できない場合があり、同僚や他部署の社員など、多様な関係者の視点を取り入れた360度評価が注目されるようになりました。
2.3 人材育成の重要性
少子高齢化の深刻化により、近年、人材の確保が困難な状況が続いています。中小企業の場合、大企業よりも人材の確保が難しいため、入社した人材を大切に育成し、離職を防ぐための対策を講じなければいけません。
人材を育成するうえで課題となるのが、「せっかく採用したにもかかわらず、早期に離職する場合がある」という点です。直属の上司のみの評価では、納得できずに離職に至る可能性があるのでご留意ください。360度評価で、さまざまな関係者の判断を示せば、納得しやすいため、離職の防止に役立つでしょう。
3. 360度評価のメリット
以下、360度評価のメリットを3つご紹介します。
3.1 多角的な視点からの評価
360度評価では、上司だけではなく、同僚や他部署の関係者など、多種多様な立場・視点から判断が実施されます。直属の上司1人に判断を任せると主観的・感情的な要素が入り込むおそれがありますが、数多くの関係者が関与すれば客観的で公平・正確な評価が可能です。
なお、同僚同士が評価を実施する場合、「匿名」による評価システムでは「ライバルを蹴落とし、出世しよう」と考える社員がほかの社員に対して厳しい判断をしがちなので、「非匿名」による評価システムのほうが望ましいとされています。
3.2 社員の成長促進
自分自身では「これが正しい」と思っていても、他者から見れば「間違っている」というケースがしばしばあります。
360度評価によって多数の関係者から指摘を受ければ、自己認識と他者評価のギャップから気付きが促され、成長につながるでしょう。
3.3 組織の透明性向上
上司1人が主観的・感情的に評価する仕組みの場合、ネガティブな評価をされた社員が、「あの社員にはプラスの評価をしているのに、なぜ自分にはマイナスの評価をしているのだろうか」「特定の人員だけ優遇しているのではないか」などと不満・疑念を持つかもしれません。
360度評価を導入してオープンな文化を醸成すれば、組織の透明性が向上し、社員同士の信頼関係が強化されるでしょう。
4. 360度評価の導入ステップ
以下は、360度評価を導入する大まかな流れです。
- 目標の明確化
- 評価項目の設定
- 評価者の選定
- 実施とフィードバック
各ステップに関して説明したうえで、制度構築に関する注意点をご紹介します。
①目的の明確化
新たな評価制度を導入する際は、目的を明確化し、組織内で共有することが重要です。
360度評価を導入する場合は、多角的な視点からの評価を実現し、社員の成長を促進し、組織の透明性を向上することが目的であると社員に伝えましょう。
② 評価項目の設定
「人事評価制度」という単語を見聞きした際に、「役職・部署ごとに、細かい評価項目が一覧表の形で定められている」というイメージを抱く方がいるかもしれません。人事部に大量に人員が配置されている大企業であれば、そのような対応が可能でしょう。
しかし、中小企業では、「人事部がない」「総務部が人事も担当している」といったケースもあるのではないでしょうか。その場合、詳細な内容の人事評価制度を構築しても、実際には運用できない可能性があるので、項目数を極力抑えるべきです。
具体的な評価項目は、以下に示す3種類の目標を踏まえて設定し、文書化してください。
- 成果目標(業績を向上させるための役割など)
- 能力目標(目標を達成するための能力・知識・資格など)
- 情意目標(業務に対する姿勢や考え方)
また、会社の理念・ビジョンに関連する内容も盛り込み、営業部・管理部・製造部など、部門ごとに項目を設定することも検討しましょう。
③評価者の選定
360度評価では、上司だけではなく、同僚も評価者になる場合があります。しかし、「同じ部署で年次が近いメンバー」は、ライバル(昇進確率が自分と近い人員)を蹴落とそうとして、正直な感想よりも低めに評価する傾向があることにご留意ください。
公正な評価を実現するために、同じ部署で年次が近いメンバーは避け、異なる部署の社員を評価者として選ぶことも検討しましょう。
④ 実施とフィードバック
項目別に「A~C」や「1~5点」といった記号・数字を記入する形式の「評価シート」を作成し、評価者が点数を付けましょう。
なお、面談してフィードバックを実施することが大切です。事前に面談シートを作成し、何を話すのか、何を聞くのかを明確にし、漏れがないようにしておきましょう。面談シートを残しておけば、後日、フィードバック担当者が交代しても、これまでの経緯を把握できます。
制度構築の注意点
評価制度は、会社のカルチャーを踏まえて構築することが大切です。社内事情を反映したオンリーワンの制度を作り上げましょう。ただ単に360度評価制度を導入するだけでは、効果が出ないどころか、これまでの会社の文化が破壊される結果、逆効果となる可能性もあるのでご注意ください。
なお、ノウハウを有する人材がおらず、社内で制度を構築することが難しいと感じる場合は、「人事のプロ」に外注することも選択肢として検討しましょう。
5. 360度評価の評価項目例
以下、360度評価における評価項目の具体例を4つご紹介します。
5.1 リーダーシップ
リーダーシップとは、会社の理念・価値観に基づいて魅力ある目標を設定し、メンバーの意欲を高めながら実現に向けて行動することです。組織は個人の集合体であるため、組織全体が動くためには、優れたリーダーが個人に働きかけることが重要です。
評価シートに「リーダーシップ」に関する項目を盛り込み、「社員をまとめ、目標に向かって導くことができるかどうか」を評価者に評価してもらいましょう。
5.2 コミュニケーション能力
コミュニケーション能力とは、スムーズに情報を共有したり、意思を疎通したりする能力です。効果的なコミュニケーションを実施すれば、自分の考えを伝えつつ、相手の考えを酌み取りながら巻き込むことが可能になるでしょう。
評価シートに「コミュニケーション能力」に関する項目を盛り込み、「課内・社内問わず、積極的にコミュニケーションを図ることが可能かどうか」を評価者に評価してもらいましょう。
5.3 問題解決能力
問題解決能力とは、「課題を正しく理解し、解決策を立案して実行したうえで、結果を検証して計画の見直しや次の計画に反映させる能力」です。
多くの中小企業では、ITの利活用が進んでいないことや、価格転嫁力がないことが課題として挙げられます。「ITスキル」や「価格転嫁するための交渉力」に関する項目を評価シートに盛り込んで、評価者に評価してもらうことを検討しましょう。
5.4 チームワーク
中小企業など、比較的少人数の組織では、チームワークが重要になります。会社においてチームワークとは、社員が同じ目標を達成するために共同作業を実施することを意味します。
評価シートに「協調性」に関する項目を盛り込み、「自分の都合にとらわれず、他者と協
力して業務を推進できているかどうか」を評価者に評価してもらいましょう。
6. 360度評価導入の注意点
以下、360度評価を導入するうえで注意するべき点を3つご紹介します。
6.1 匿名性の確保
評価者と被評価者の間に「従属関係(上司・部下の関係)」がある場合は、「匿名」のほうが自由な評価が可能であり、より真実に近い評価が得られます。被評価者に対して、評価者が誰なのかを伏せた状態で評価を実施してください。
ただし、上述したように、「同じ部署で年次が近いメンバー」が評価者となった状態で、匿名で実施すると、ライバル(昇進確率が自分と近い人員)を蹴落とそうとして、正直な感想よりも低めに評価がなされる傾向があります。
正確な評価を得るために、「同じ部署で年次が近いメンバー」を評価者に選定する場合に関しては、非匿名で評価してもらうべきです。あるいは、「同じ部署で年次が近いメンバー」を評価者から排除したうえで、他部署のメンバーなどに匿名で評価してもらうことも検討しましょう。
6.2 評価バイアスへの対策
評価者も人間である以上、個人的感情や先入観によって、評価が歪む可能性があることにご留意ください。寛大化する場合もあれば、厳格化する場合もあります。
歪みを防止するために、事前に評価者に対して評価方法に関する教育・訓練・研修を実施しましょう。
6.3 結果の適切な活用
「評価を実施したら、それで終わり」ではなく、結果を人材育成や組織改善に活かしましょう。評価結果を踏まえ、能力が発揮できる部署に各社員を配属し、教育・研修を実施してください。
1人2人の社員ではなく、多くの社員に課題が見出される場合(例えば、ITに関するスキルが低い社員が多い場合)は、組織全体の問題として受け止め、パフォーマンスを改善するための方策を検討しましょう(「資格取得を推奨し、費用を補助する」「DXの推進に取り組んで、全社的にスキルの底上げを図る」など)。
7. まとめ
360度評価とは、さまざまな角度から(上司の視点だけではなく、同僚や部下、他部門の関係者などの視点も取り入れて)社員を評価する手法です。
数多くの関係者が関与するため、客観的で公平・正確な評価が可能になります。社員の成長促進に役立ち、組織の透明性向上にもつながるので、導入を検討してはいかがでしょうか。
導入する際には、目的を明確化したうえで、評価項目を設定してください。そして、評価者を選定して評価を実施しましょう。実施後には、被評価者へのフィードバックも忘れてはいけません。
なお、360度評価の仕組みは、会社のカルチャーを踏まえて構築する必要があります。ノウハウを有する人材がおらず、社内で制度を構築することが難しいと感じる場合は、「人事のプロ」に外注することも選択肢のひとつです。

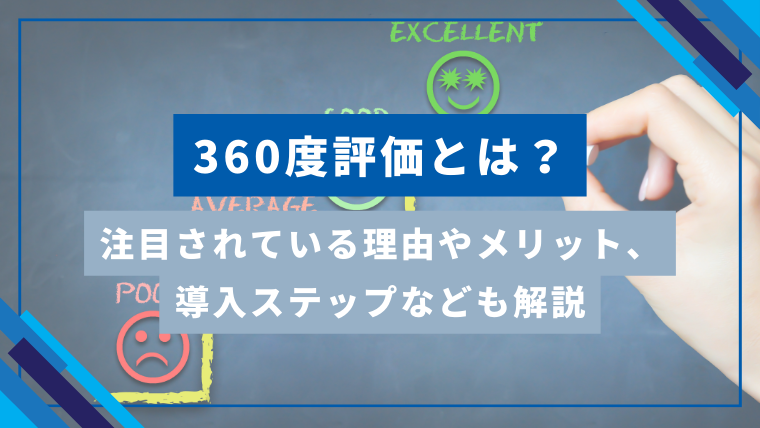
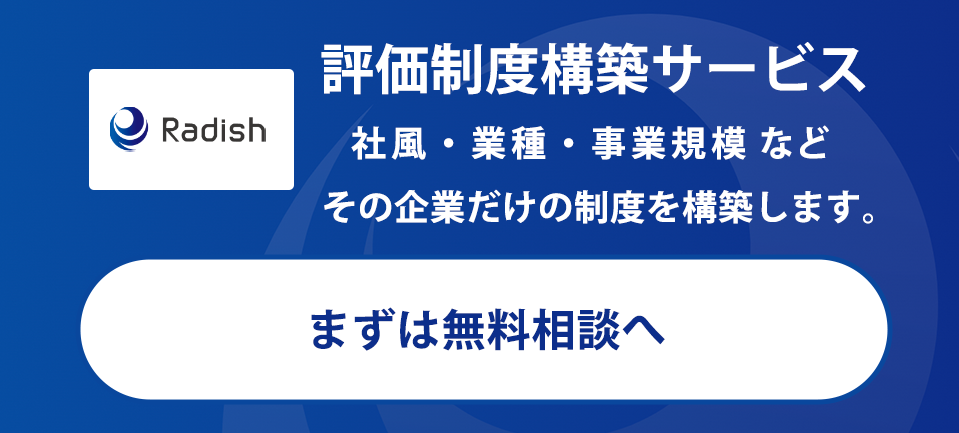

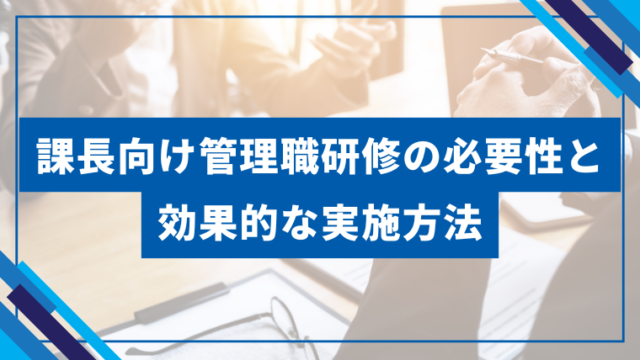
とは?-640x360.png)